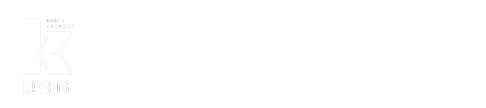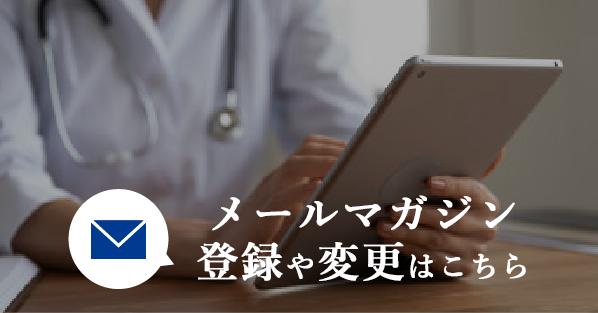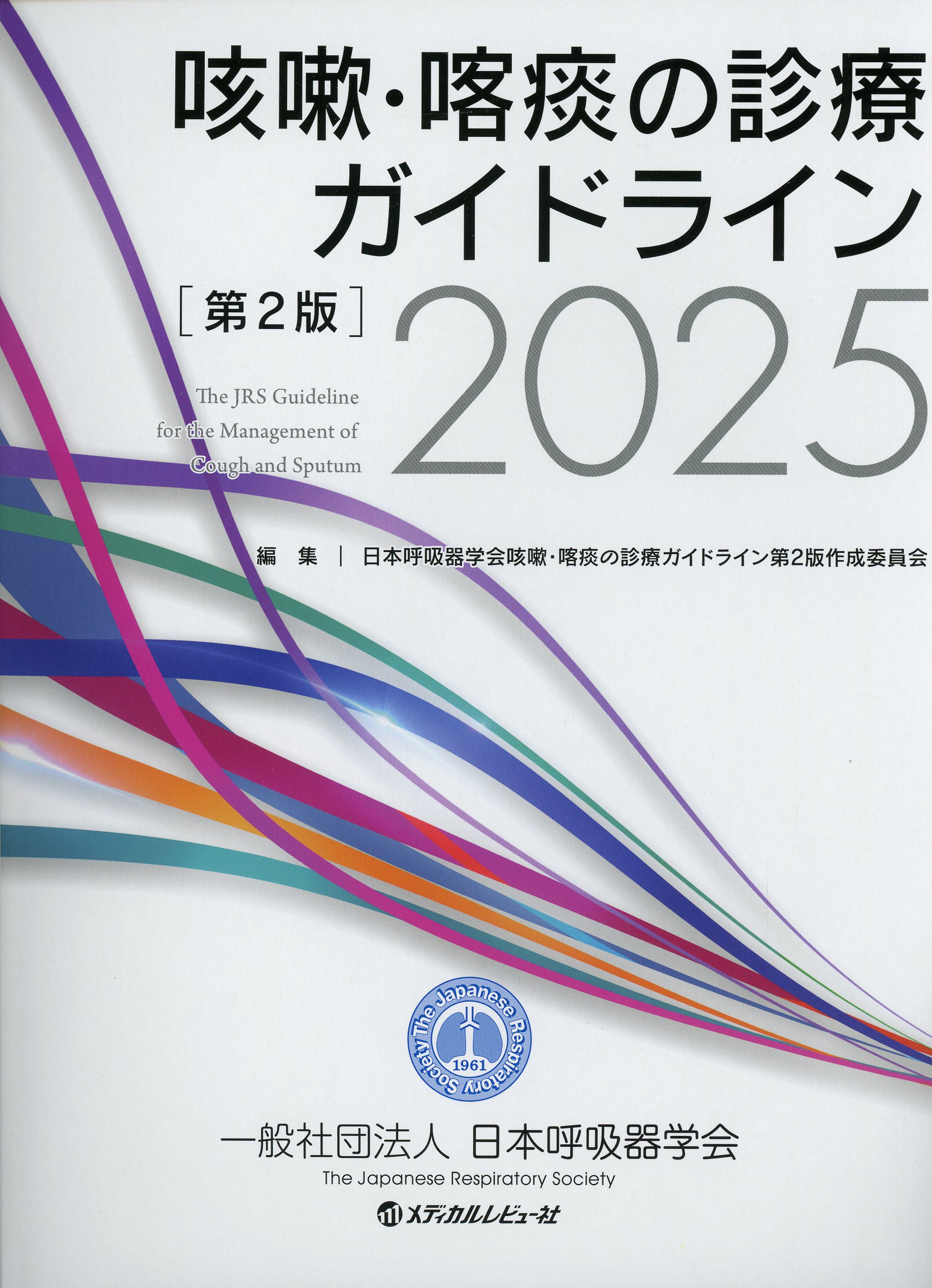咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版2025
日本呼吸器学会 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版作成委員会 ・編
【目次】
Chapter 1 緒言
Chapter 2 咳嗽総論
Chapter 3 喀痰総論
Chapter 4 主要な原因疾患
Chapter 5 小児
Chapter 6 Clinical Question
Chapter 2 咳嗽総論
Chapter 3 喀痰総論
Chapter 4 主要な原因疾患
Chapter 5 小児
Chapter 6 Clinical Question
【記事】
咳嗽は呼吸器疾患の日常診療において最も高頻度に遭遇する症状の1 つであり,とりわけ長引く咳や頑固な咳で医療機関を受診する患者さんは年々増加の一途を辿っています。日本呼吸器学会では,2005 年の『咳嗽に関するガイドライン』初版に引き続いて,2012 年に第2 版を,さらに2019 年に『咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019』を発刊しました。2019 年版ではタイトルからもおわかりのように,咳嗽のみではなく,密接に関連している「喀痰」も含めた診療ガイドラインとなりましたが,喀痰のガイドラインは当時世界初となりました。2019 年版で新規に取り上げた「感染予防策」は2019 年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに大いに役立ったのではないかと思いますし,この版で新たな概念として取り上げた「咳過敏症」に関してはその後のP2X3 受容体拮抗薬の使い方の参考になったのではないでしょうか。2019 年以降もさまざまな咳嗽や喀痰に関する考え方の変化,新たな咳嗽に対する薬剤としてP2X3 受容体拮抗薬の発売が行われるなど,改訂の必要性が生じ,今回の発刊となりました。
今回,このガイドラインで初めて試みた9 つのクリニカルクエスチョン(CQ)に対するシステマティックレビュー(SR)や巻頭フローチャートの改訂に時間を要しましたが,ようやく『咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2 版2025』の発刊にこぎつけました。
本ガイドラインは,咳嗽・喀痰の診療を種々の側面で支援することを目的に作成された
指針でありますが,以前のガイドラインの考え方と同様に,咳嗽・喀痰の診断法や治療法をこのガイドラインで強制するものではありません。今後も最新のエビデンスを集めながら,本邦の実情に合ったより使いやすいガイドラインへの改訂を続けていく必要があります。
今回,このガイドラインで初めて試みた9 つのクリニカルクエスチョン(CQ)に対するシステマティックレビュー(SR)や巻頭フローチャートの改訂に時間を要しましたが,ようやく『咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2 版2025』の発刊にこぎつけました。
本ガイドラインは,咳嗽・喀痰の診療を種々の側面で支援することを目的に作成された
指針でありますが,以前のガイドラインの考え方と同様に,咳嗽・喀痰の診断法や治療法をこのガイドラインで強制するものではありません。今後も最新のエビデンスを集めながら,本邦の実情に合ったより使いやすいガイドラインへの改訂を続けていく必要があります。